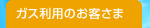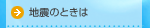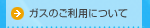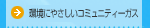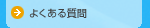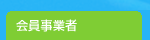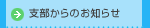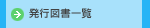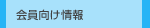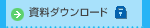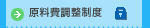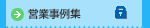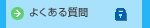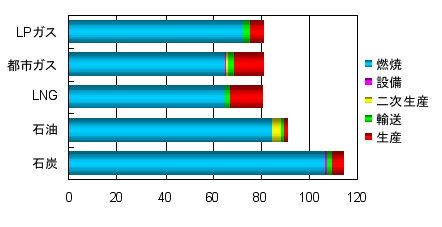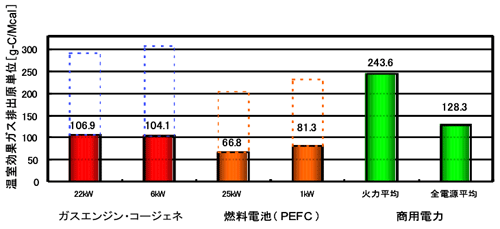「簡易ガス」から「コミュニティーガス」へ。地域とともに歩むコミュニティーガスをこれからもご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。
|
コミュニティーガス事業とは - より詳しい説明
コミュニティーガス事業の誕生
液化石油ガス(LPガス)が家庭用燃料として脚光を浴び、それまで使われてきた木炭、練炭などの固体燃料に代わって普及しはじめたのは昭和30年頃からです。しかし、当時は容器(ボンベ)にLPガスを充てんして各戸ごとに取り付ける供給方式がとられていました。
その後、昭和40年頃から都市周辺部で住宅団地の造成が急激に増えはじめ、これらの団地にLPガスを導管で供給する「導管供給方式」が各地で採用されるようになりました。 このような情勢に伴って、国は70戸以上の団地に対する導管供給事業を公益事業として取り扱うこととし、昭和45年4月に「ガス事業法」を改正して、これを簡易ガス事業と規定し、同法を適用することになりました。 それ以後、簡易ガス事業は、その供給方式の簡便性、需要に対する迅速性、経済性などが高く評価されて全国的に普及し、地域の発展に寄与してまいりました。 平成29年4月に改正ガス事業法が施行されたことにより、法律上、旧簡易ガス事業は「ガス小売事業」の一部(ガス事業法第2条第1項括弧書きに規定するものに係るガス小売事業)となりました。協会ではこれを「コミュニティーガス事業」と呼称することとなりました。 コミュニティーガス事業には安定供給が課せられています
コミュニティーガス事業は、ガス事業法により安定供給が課せられています。コミュニティーガス事業は、住民の日常生活に不可欠なガスを、ガス事業法に基づいて登録された供給地点(戸)に導管で供給するガス小売事業です。
改正ガス事業法に則り、事業者はガス小売事業者の登録を行い、安定供給に必要な規模の特定ガス発生装置を用いて小売供給していますので、需要家の皆様に安心してガスをご使用いただけます。
保安管理には万全を期しています
特定ガス発生設備や導管などのガス工作物は、経済産業省令で定められている技術上の基準に適合するように施工し、経済産業局が行なう使用前検査に合格しなければ使用することができません。
また事業開始後においても、技術上の基準に適合するように維持、管理することが義務付けられています。 ガス工作物の工事や維持などについては、国家試験に合格したガス主任技術者の監督の下に行われています。ガス主任技術者は、団地ごとに選任されており、その職務内容は「保安規程」に定められています。 この保安規程には、このほか保安管理体制、保安に係る巡視点検・検査、災害等非常の場合の措置などを定めて経済産業局長に届け出るとともに、コミュニティーガス事業者はこれを順守することが義務付けられています。 なお、経済産業局長は保安を確保するために必要があると認めるときは、保安規程の変更を命じることができることになっています。 コミュニティーガス事業及びLPガス(コミュニティーガス事業の主たる燃料)の特徴
コミュニティーガス事業は、旧一般ガス(都市ガス)供給区域外のいわゆる郊外住宅団地において、団地内に設置した特定ガス発生設備を中心とした小規模な導管網で団地内へガスを供給しています。また、主たる燃料であるLPガスは、天然ガスとともにクリーンなエネルギー源であり、可搬性・貯蔵性に優れており、災害時の緊急用エネルギー源としても幅広く活用されています。以下にコミュニティーガス事業及びLPガスの特徴を整理します。
大型団地にも供給されています
コミュニティーガス供給システムを採用している団地の大部分は1,000戸未満です。 その構成率をみますと70戸以上100戸未満が約10%、100戸以上300戸未満が約33%を占めています。
一方、1,000戸以上は約22%となっていますが、これらの大型団地でもこのシステムが採用されており、そのなかで最大規模の団地は、北海道の「北広島団地」
(7,358戸・平成28.3.31 現在)です。
高層マンションにも供給されています
和歌山県白浜町椿温泉にあるリゾートマンションは、 コミュニティーガスの供給が行なわれている建物としては最高のものです。地上28階、地下1階、戸数396で、地表からの高さは100メートルを超す高層マンションです。
|
|||||||||||||||||||